
バイブレーションのサイズで変わるシーバスの狙い方
-

-

-

-

-

-

-

-
2
- 9,610 views
はい。
今回は、ルアーサイズによる釣り方の違いについて。
バイブレーションの中でも、素材や形状によって得意な状況が変わってくるという記事を書きましたが、ルアーサイズに関しては、「7cm程度の大きさを一つの基準」として、目的に合ったサイズを選ぶと、使い分けやすいという話もしました。
※参照記事
「シーバス釣りで使うバイブレーションの特徴と使い方」
同じシリーズのバイブレーションであっても、サイズによって用途が変わってくるので、レンジバイブを例に、4~5cm程度といった小型、7cm程度の中型、9~10cm以上の大型サイズに分類して、狙い所の違いについて書いてみたいと思います。
横の動きとアピールを意識した大型サイズ
大型サイズの特徴は、表面積を活かしたフラッシング効果と、重量が増える事による沈下スピードの速さ。アピール力が高まるので、魚を寄せ(気付かせ)やすく、水深のある場所でも目的のレンジまで素早く沈める事が出来ます。
これらの特徴から、シーバスの回遊を待っている時や、変化の少ない釣り場で遠投して広範囲を探る場合、横方向(リフトアンドフォールを含む)の釣りといった感じで、釣り人側からアピールしたい状況に向いているかと。
一方、デメリットとしては、バラシが増えてしまう可能性も。重量のあるルアーを使うと、エラ洗いの際に「身切れ」や「フックアウト」の可能性が高くなります。更には、遠い場所でのヒットが増えるので、フッキングの力が伝わり難い事も。
シーバスを探しながら、広範囲に攻める釣りを展開できる大型のバイブレーションですが、ルアー重量とヒットゾーンまでの距離が増える事により、バラしてしまう可能性も高くなるので、フッキングと魚のやり取りは注意が必要になります。
縦の動きと食わせを意識した小型サイズ
小型サイズの特徴は、何と言っても「沈下スピードの遅さ」と、ピリッと光る「細やかなフラッシング」にあるかと。大型のバイブレーションは、「広く探る釣り」が特徴でしたが、小型の場合は「居る場所に投げて食わせる釣り」に最適。
例えば、下記のような「明暗・流れ・橋脚」が絡むスポットがあった場合。明暗の境目から橋脚の両サイドにかけて、シーバスが居るだろうと予想できます。
こういった場所に対して、小型のバイブレーションを投げ入れ、アクションをつけながら即座に巻き始めると、一投目から食ってくる事が多々あります。これは、小型にしか出せない「リアクションバイト」よるものかと。
今回は、明暗を例に挙げましたが、護岸沿いや水面に突き出ているキワといった感じで、「上を意識しているシーバスが居る」と思うスポットに対して有効なので、ルアーを食わせに行くのであれば、小型のチョイスといった使い分けも。
バランスが取れた使い心地の中型サイズ
シーバスへのアピール・食わせリアクションと、何かに特化している訳ではありませんが、リトリーブの抵抗やキャスト感といった、トータル的なバランスが取れているのは、中型サイズのバイブレーションになるかと思います。
大型サイズよりは扱いやすく、小型サイズよりはアピール力が高い。この中型サイズを基準に、アピールを増やすのであれば大型、食わせるリアクションを狙うのであれば小型といった、バイブレーションサイズの使い分けで良いように思います。
ルアーサイズで変わるシーバスの狙い方・まとめ
今回は、レンジバイブを例に挙げて、各サイズの特徴を書いてみましたが、他のルアーの場合でも、重さやサイズを基準に選べば、同じような使い分けが出来るかと。
自分の場合、バイブレーションに関しては、中型~小型を使う事が多く、タックルバランスやバラシの観点から、大型サイズを使う事は少ないように思います。やはり、深夜の明暗や護岸沿いで活躍するのは、小型サイズのチョイチョイアクション。
小型サイズであれば、一定層を通しやすく、沈下スピードも緩いので、ルアーを長く滞在させる事が出来ます。また、表層を意識しているシーバスが居れば、数投で反応を得られる事も多いので、ここぞという時に登場する愛用のルアーです。
一方、シャローフラットが続く変化の少ないサーフや、堤防といったオープンエリア、初夏のデイゲーム等では、大型バイブレーションの方が使いやすいかと。
バイブレーションの使い分けに関しては、重量による沈下スピードの違いと、表面積によるフラッシング効果の強弱、ボディサイズによるアクションのキレ具合なんかを意識し、状況に合わせて選ぶと良いように思います。
シーバス関連に関するお知らせ
現在、シーバス釣りに関する内容は、新ブログ『まころぐ』にて更新中です。当ブログよりも、丁寧に解説するよう心掛けていますので、宜しければチェックしてみて下さい!!
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。今回の投稿と同じカテゴリーにある、次の記事は「ルアーとラインの結束・簡単で強度が高いパロマーノット!」、前の記事は 「シーバス釣りで使うバイブレーションの特徴と使い方」となっております。
-
思いがけない夏のプレゼント!ありがとう!ばんぱくサンタ!!
2024年7月24日

-
ボートシーバス用ジギングロッド”オーシャンフィールド”のインプレ
2024年7月21日

-
キャスト練習は強制終了!!
2024年7月18日

- 【車の傷】リアバンパーを自分で修理!工程③プラサフ下地編 2024年7月14日
- くらしのマーケットでエアコン洗浄!予約手順と体験レビュー!! 2024年7月11日

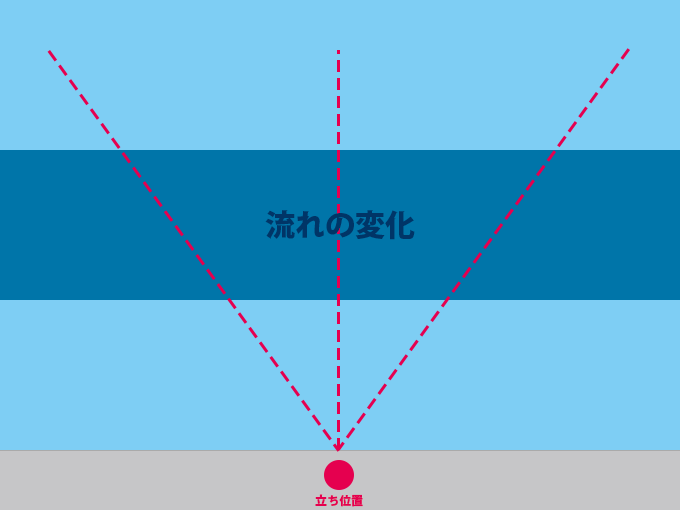
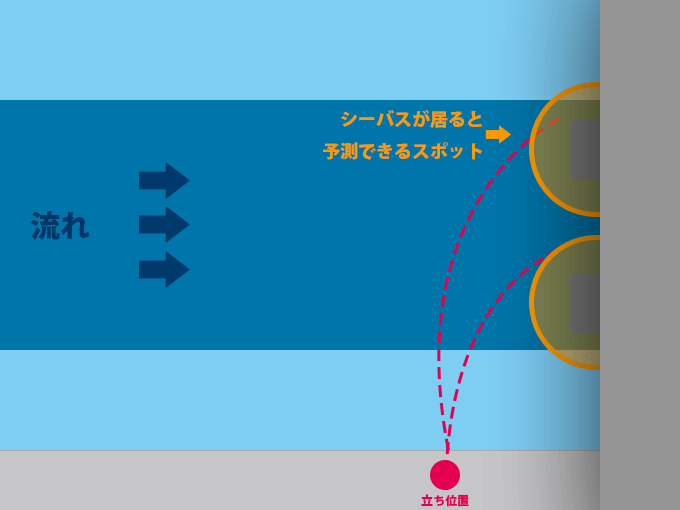






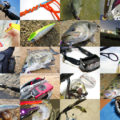









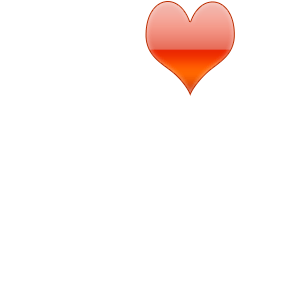
 CATEGORY
CATEGORY




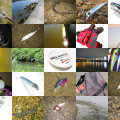










いつも分かりやすい解説ありがとうございます!
いつか今度ロッドについて書いてください!
そんなにロッドを何本も持ってるわけじゃ無いんですけど選び方もそうですけどハイエンドモデルの違いがなかなか分かりません。
高いロッドだとエクスセンスを持ってて確かに良いんですけどもう一つ持ってるラブラックスと極端な違いも分かりません。 もしかしてラブラックスで十分かもなんて感じてます。なのでロッドについていつか教えてください。まあ、結論は使って楽しめるならなんでも良いんじゃ無いの?なんて感じです。
コメントありがとうございます!!(^^ゞ
ハイエンドモデルの違いですか~。
たかすぃーさんも書かれていますが、価格の差というよりは、自分の使用条件に合うかといった「使用感」が重要になってくるかと。ロッドを選ぶ際の項目としては、長さ・硬さ・重量・グリップ形状等が挙げられますが、新しいロッドが欲しくなる場合、使用中のロッドの何処かに、不満や改善したいと思う点があると思います。
それらを改善する為に、本に掲載されている広告やメーカーのホームページから条件に近い商品を探し、ブログやレビューを読んで検討すると思いますが、価格うんぬんの前に、気に入るかどうかは実際に使ってみないと分からないのが本音。
自分の場合、アーバンサイドカスタムとのフィーリングがしっくり来たので、1本を使い回しつつ長く使っていますが、それまでは取っ替え引っ替え色んなロッドを使っていました。なので、値段やハイエンドモデルというよりは、使用感がピタッとくる事が一番大事な気がします。
値段やブランド名が先に来るのでは無く、使った感触が最優先というか…。エクスセンスを振らせてもらった事もありますが、自分にとってはハリが強すぎる印象でしたし、アーバンサイドカスタムを振ってもらった事もありますが、頼りないイメージとの感想を頂いた事もありますし。
最終的に、長さ・硬さ・重量・グリップ形状等を含めて、自分が使いやすいと思う物を選べば良いように思います。※まぁ、色んなロッドを振れる機会は少ないんですが…。
単純なハイエンドモデルの違いを挙げれば、使われている素材や加工方法の違いであったり、開発に費やしたコストやネームバリューといった点になると思います…(^_^;)