
シャローではレンジ調整不要なの?!サヨリパターンまとめ
- 投稿日2014.11.07
-

-

-

-

-

-

-

-
4
- 7,541 views
はい。
今回は、水深の浅いエリアで釣りをする際のレンジについて。
一般的に「シャローはレンジを探らなくていいから楽」というように言われますが、厳密に言うと「レンジを探らなくていい」のでは無く「探るレンジが絞り込める」だと思います。
水深があるエリアの場合、シーバスが居ると思われる場所(面)と、反応してくれるレンジ(縦)を探さなくてはなりません。一方で、水深の浅いエリアだと、シーバスが居る場所の見当がつけば、後は縦のコースを決めればいい。
ただ、これがシビアな時もあります。
以前ほど釣りに出掛けてないので、日ムラによる違いか今年がそうなのかの検証はできませんが、今年のサヨリパターンは全体的にシビアな感じでした。なので、今年のサヨリパターンを例にして、水深の浅いエリアでの釣りの話を書いてみたいと思います。
水深の浅いエリアについて
まず最初に、ボートに乗って沖で釣ったり、オカッパリで気軽に釣ったりと、いろんなシーンで釣れるシーバス。水深が股下程度の浅い場所でも釣れてしまいます。水深が違っても、それぞれの場所でシーバスが釣れるという事は、各エリアで捕食を行っているから。
色々とある捕食エリアの中でも、水深が浅いという事は、自身の体が傷付いたり外敵からの危険にもさらされる。シーバスにとってリスクの高い場所が水深の浅いエリアだと思いますが、そのリスクを取ってまで浅い場所に来ているシーバスは「食べる」事に意識を強く持っているはず。
その理由として、エサが豊富に集まる。もう一つは、エサを食べやすい。
季節によりベイトの接岸状況は変わりますが、捕食を目的に動き回って体力を消耗するよりも、身近に食べるのもがある状況の方がシーバスにとっては重要なんだと思います。
では、なぜシーバスにとって「水深の浅いエリア」がエサを食べやすい場所になるのか。答えの一つとして、エサが逃げないように壁を作る事が出来るからではないでしょうか。
例えば、飛んでいるハエをパチンと仕留めるのは難しいですが、壁に張り付いて動いているハエならパチンと出来る。これと同じような事が、水中でも起こっています。
水面を壁にする
代表的な例が、それ以上逃げる場所が無くなる水面を壁にして食ってくる、上方向を意識している状態。春のバチシーズンや秋の荒食い時に、水面がボシュっと音を立てて割れる、ドキドキの状況です。
エサとなるベイトの下側から上方向を意識して、捕食のタイミングで上昇してガバっと食べる。こうなると、上方向には水面の壁が出来てベイトは上方向に逃げられない。シーバスにとっては、捕食がしやすい状況になります。
先月シーバスを釣ったパターンが、まさにこの通り。
使用しているのはパラガスですが、キャスト後はロッドを立ててテンションを張らず。バチシーズン時のように引き波を立てながら、ルアーを潜らせる事無く引いてくる。
イメージとしては、シーバスのアタックでダメージを受け、水面を漂っているサヨリ。少しでも潜らせてしまうと反応が出ない。そんな状況が続いてました。
ボトムを壁にする
前項と真逆なのが、ボトム(海の底)を壁に使って捕食を行っている状況。イワシやサヨリといったベイトが大量に接岸している場合、斜面のある地形ではボトムと水面の2方向をカットして追い込み、波の間から飛び出してくる程の足元で捕食している事もしばしば。
季節が進んで、ボトムに居るカニやエビが捕食対象になると多くなるパターンだと思いますが、水面と同様にボトムに関してもシーバスがエサを食べやすい状況を作り出しています。
前回の釣行がこのパターン。先月はバチシーズンのような釣り方でないと反応しなかったのが、今回は真逆。
着水直後からダッシュで糸フケを取ってロッドを下に構え、チョイチョイアクションでルアーに水を掴ませ、ブリブリと潜らせる。ボトム付近を早巻きで引いてくると、簡単にバイトが出る状況でした。
シビアなレンジ調整
前回の釣行で持っていった、6番フックを装着したパラガスと4番フックのパラガスですが、釣行の際に両方使用してみました。
最初は6番フックのパラガスでバラしが続き、針掛かりの改善やレンジも(下だったので)含め、4番フックのパラガスが合うだろうと思い投げてみましたが、直後からピタっと反応が無くなり。数投してから、試しに6番フックへ戻してやると、1キャスト数バイト状態に。
先月は、キャスト直後に内蔵されているウェイトも戻さないイメージで超デッドスローに引く。少しでも潜ってしまうと反応が無くなる状態。フックサイズによるアクションの違いはあるものの、今月はフックサイズ分の違いで反応が変わるシビアな感じ。
シャローでのレンジ調整まとめ
今回の例は、上か下かの両極端な話しでしたが、冒頭でも書いたように「シャローではレンジを探らなくていい」のでは無く、「探る範囲が絞られている」だけ。
ベイトの有無や水温、流れや濁り方。その時の状況によってシーバスが反応してくれるレンジが変わると思いますが、浅いエリアだからこそ、今回のように同じルアーをつかっても、フックの重さ程度の差で違いが出る事もあります。
浅いからといってササっと終わらせてしまうと、釣れる魚が居ても釣らないまま終わってしまう。なんていう寂しい感じになってしまうので、浅いエリアではレンジの絞込みが可能な分、同じルアーでもリトリーブ速度やロッドの角度を変えてみて、反応が出るパターンを探すのが重要かと思います。
シーバス関連に関するお知らせ
現在、シーバス釣りに関する内容は、新ブログ『まころぐ』にて更新中です。当ブログよりも、丁寧に解説するよう心掛けていますので、宜しければチェックしてみて下さい!!
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。今回の投稿と同じカテゴリーにある、次の記事は「今年はルアーロストがゼロ!根掛り対策とルアーの外し方!!」、前の記事は 「海釣りルアーの結び方!図解版・簡単クリンチノット!!」となっております。
-
ボートシーバス!長男君は初めてのシーバス釣果!!
2024年4月21日

-
人生初ボートシーバスで連発二桁釣果!キャプテンに感謝!!
2024年4月16日

- 2024年のシーバス釣り始動!! 2024年3月20日
- IP-10 HIGH&LOW(アイアンプレート ハイアンドロー )を投げる日 2023年11月5日
- クロスバイクのグリップ交換手順とエルゴグリップの角度 2023年10月29日

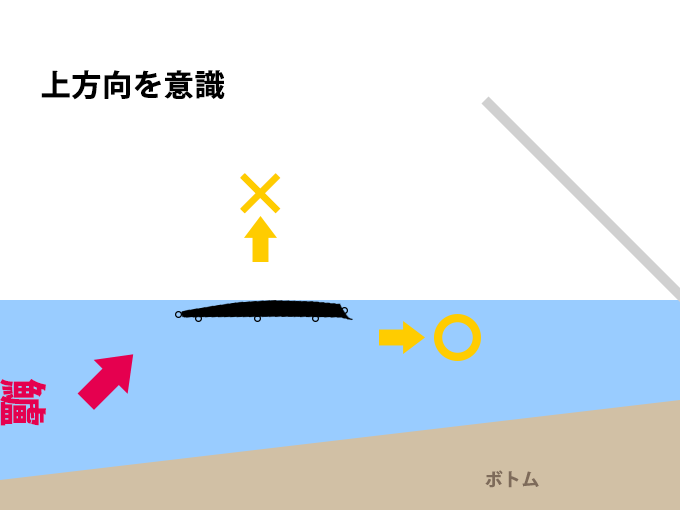
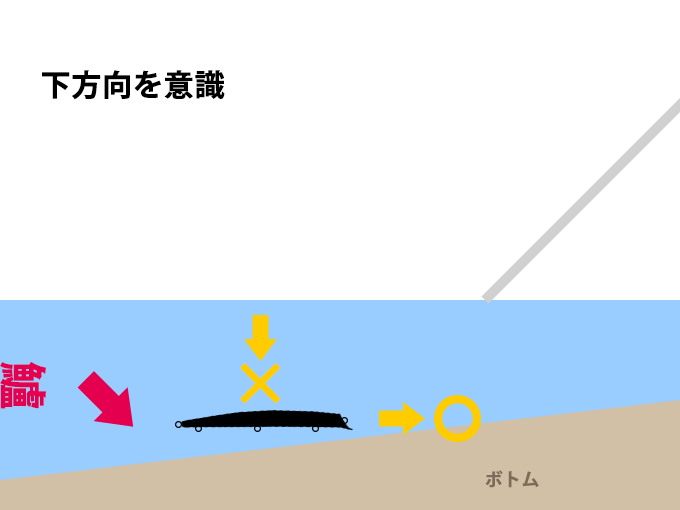




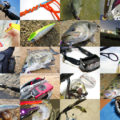









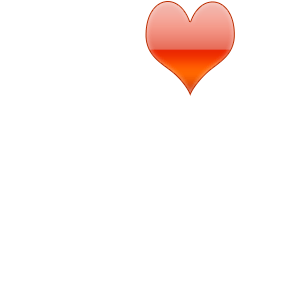
 CATEGORY
CATEGORY




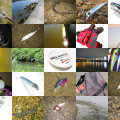










なるほど、勉強になります。
僕もリトリーブスピードによって、釣果が変わるのを何度も経験しました。
バチシーズンでも早巻きで連発とか。
あれこれ試行錯誤しての1匹は最高に気持ちいいですねー。
サヨリパターン、行きたくなりました。
やはり長時間釣行かな?笑
色々探って、反応が出た時「あぁ、コレか!」って思った瞬間が楽しいですね。
そこから微調整して釣れると、メチャ嬉しくなります(*^_^*)
自然相手の遊びなんで、それが正解なのか、それでも少し間違っているのかの答えは藪の中ですが、別に学校のテストをやっている訳では無いので、自分が楽しめばそれが正解でOKなんじゃないかと(笑)
長時間釣行…。家族サービスはタップリしてあります??(笑)
先日は、かなりタチウオが入って来ていたので、ラインを切られないように気をつけて下さいね~!!(^^ゞ
どうもです。
まさに、レンジを意識する事は大事ですよね。
今夜も、全くダメなのか?と思いきや、ちょっと目線を変えるとヒットが連続しました。
ほんの少しの事なのですが、反応が変わるのが面白いですね〜^_^
普段と違ったアプローチをしてあげると、反応が出る事ありますよね!
特に、シャローでの釣りは、その調整がシビアな分、その日のパターンを掴んでしまえば、ある程度釣り続ける事も可能なんで、それが楽しいです。
まぁ、パターンが見つけられなければ、ガックリと肩を落として帰るんですが…(笑)
いつもはこう!だけだと分からない事もありますが、違った事をして掛ける事ができれば、自分の中の引き出しも増えますし、何故そうなったかを考える楽しみも増えますし(^^ゞ